こんにちは、もりみつです。
どんな分野でも、新人さんがぶち当たる壁があると思います。
それは、わからないことが出たときの対処法です。
だいたいの先輩は「わからないことはすぐ聞いて」と言ってくれます。
一方で、わからないことを聞いたときに「そんな簡単なこともわからないの?」と嫌な顔をされる機会もあるのではないでしょうか。
と、モヤモヤすることがあると思います。笑
今回は、そんな問題を解決する、聞くべきか聞かないべきかの判断基準を考えていこうと思います。
「調べてわかるか」で判断せよ
先輩に聞いたらダメなパターン
先輩に聞いたらダメなパターンは、ずばり、自分で調べたらすぐにわかることです。
用語の意味とか、世の中の仕組みとか、そんなのは5~10分調べればだいたい理解できます。
そういうことは、先輩に聞いたらダメです。Google先生に聞きましょう。
質問する立場であれば、知識を得るためにかかる時間は、自分で調べる場合でも、人に教わる場合でも、おおよそ5~10分くらいです。かかるコストは同じくらいですね。
一方で、人に教わる場合は、教えてくれる人の時間も同様にかかっています。ということは、同じことを理解するまでにかかるコストは、2倍かかっているということです。
無駄ですよね。
だから、聞かれた先輩も「そんなこと聞かないで自分で調べろよ…」と思ってしまうわけです。
まずは、わからないことは自分で調べましょう。
先輩に聞くべきパターン
考えないとわからないとき
「調べてもわからないこと」が出てきた時、みなさんはどうするでしょうか。
まず、「自分で考える」と思います。だって、調べてもわからないんだから。
考えるのはとても良いことです。
(この問題は、ひょっとしたらこうすれば解決するのかな~) など、まずは自分で考えてみましょう。
しかし、自分の考えで導いた答えが正しいかどうかは、確認する必要があります。
あくまでも自分の考えなので、他の人がどう考えるかはわかりません。
そこで、「先輩に聞く」という選択肢が出てきます。
考えないとわからないことは、「100%の正解」は存在しないと思ってよいでしょう。
そんな時は、「経験」がものを言います。最適解を導き出すのは「経験」なのです。
そして、経験を積んでいるのは先輩たちです。
なので、先輩に必ず聞きましょう。(あくまでも、自分の考えを持った上でですが)
逆に、聞かないと絶対に怒られます。
「なんで自分だけで判断したんだよ!すぐに相談しろって言っただろ!」と。
ということで、自分で考えて意見を持った上で、先輩に確認しましょう。
調べてもすぐにわからないとき
調べてわかることは聞くなと言いましたが、調べるのにあまりにも時間がかかる時は別です。
全く見当もつかないことを調べる時は、自分一人で解決することは無理だと思います。目安として、15分くらい調べてみて見通しが立たないときは、あきらめて誰かに聞いてください。
誰かに15~30分ほど教えてもらうだけで、大枠は理解できるようになると思います。少なくとも、調べたり考えたりする糸口を見つけることができます。
一人で立ち向かっても、1日中Googleと向き合って成果0で終わります。時間の無駄です。そんなことしてると怒られます。
「お前が無駄に過ごしたその時間も、給料が発生してるんだぞ!」と。
大きすぎる敵には、自分一人ではなく、先輩の力を借りて挑みましょう。
おわりに
共有するポイントとして、
自分がやったこと + わからないこと
の構成で質問すると、怒られることはあまりないと思います。
- ここまで調べたのですが、この先がわかりません。
- こう思うのですが、この認識でいいでしょうか。
- これについて15分ほど調べてみたのですが、埒があかないので教えてください
「自分にはこれ以上どうしようもない」ということが伝われば、聞かれた側も嫌な顔はしないでしょう。努力した上でわからないことは、誰にでもありますから。
とうことで、怒られない範囲で質問を多用し、効率的に仕事をこなしていきましょう!
一人で悩んでも仕方がないですからね。
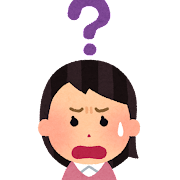


コメント